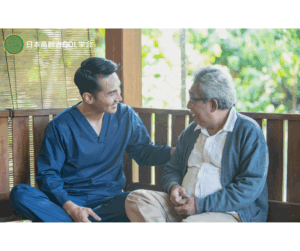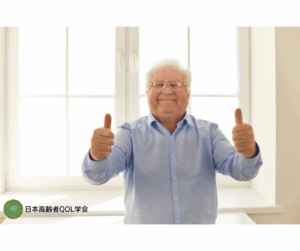前頭側頭型認知症(FTD)は、
アルツハイマー型認知症や
レビー小体型認知症と比べて患者数は少ないものの、
その症状の現れ方が大きく異なるため、
介護するご家族は特に戸惑うことが多い病気です。
記憶障害よりも、
人格や行動の変化が初期から現れるため、
「まるで人が変わってしまったようだ」と感じ、
病気だと気づきにくいケースも少なくありません。
このブログでは、
前頭側頭型認知症の主な特徴と、
介護において知っておきたい重要なポイントを解説します。
この病気への理解を深めることで、
ご本人とご家族が安心して向き合えるヒントを見つけていきましょう。
1. 前頭側頭型認知症の主な特徴
前頭側頭型認知症は、
脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで発症します。
これらの部位は、
人格、行動、言語機能を司るため、
以下のような特有の症状が現れます。
特徴1:行動・人格の変化
この病気の最も大きな特徴は、
社会的な規範やマナーを守れなくなることです。
- 症状の例
- 万引きなどの反社会的な行動
衝動的な行動が増え、
社会的なルールが守れなくなります。 - 場の空気を読まない発言
他人への配慮がなくなり、
思ったことをそのまま口にしてしまいます。 - 無関心
周囲の出来事や感情に対して
無関心になることがあります。
- 万引きなどの反社会的な行動
特徴2:常同行動
特定の行動や言動を、
同じ時間、同じ方法で繰り返す常同行動が見られます。
- 症状の例
- 同じ時間に散歩に出かける
毎日同じ時間になると、
決まった道を散歩しに出かけます。 - 同じものを食べ続ける
決まった食事しか受け付けなくなることがあります。 - 同じ言葉を繰り返す
意味もなく同じ言葉やフレーズを何度も繰り返します。
- 同じ時間に散歩に出かける
特徴3:言語機能の低下
言葉を話す能力や、
言葉の意味を理解する能力が徐々に低下していきます。
- 症状の例
- 言葉が出ない
伝えたい言葉が思いつかず、
無口になることがあります。 - 言葉の意味が分からない
物の名前が分からなくなったり、
簡単な指示が理解できなくなったりします。
- 言葉が出ない
2. 前頭側頭型認知症のケアで知っておきたいポイント
前頭側頭型認知症の特有の症状に対し、
ご家族はどう対応すればいいのでしょうか。
行動・人格の変化への対応
- 否定しない、注意しない:
「そんなことをしてはいけない」と注意しても、
ご本人には伝わりません。
否定すると、かえって反発を招くことがあります。 - 物理的な対応
万引きなどの問題行動に対しては、
ご本人が好きなお菓子や飲み物を準備しておくなど、
行動を起こす前に、別の行動に注意を向ける
工夫をしてみましょう。 - 専門家を頼る
問題行動が頻繁に起こり、
ご家族だけで対応が難しい場合は、
ケアマネジャーや専門医に相談し、
適切なサポートを受けましょう。
常同行動への対応
- 無理に止めさせない
常同行動は、
ご本人の安心感やリズムを保つためのものかもしれません。
ご本人や周囲に危険がない限り、
無理に止めさせないことが大切です。 - ルーティンを活用する
毎日同じ時間に散歩に出かけるなど、
常同行動を介護のルーティンとして組み込むことで、
介護がスムーズになる場合があります。
言語機能の低下への対応
- ジェスチャーや絵を活用する
言葉でのコミュニケーションが難しい場合は、
身振り手振りや絵カード、
写真などを活用して、意思疎通を図りましょう。 - ゆっくり、はっきりと話す
質問は一度に一つだけ、
ゆっくり、はっきりと話すことで、
ご本人が理解しやすくなります。
まとめ
前頭側頭型認知症は、
ご本人の行動や人格の変化から、
「病気」だと認識するまでに時間がかかることがあります。
しかし、
これらの症状が病気によるものであると
理解することが、
介護を穏やかに進めるための第一歩です。
ご本人を責めず、
行動の裏にある理由を探り、
柔軟に対応する。
そして、
一人で抱え込まず、
専門家や介護サービスの力を借りる。
これらのアプローチで、
前頭側頭型認知症と向き合い、
穏やかな日々を築いていきましょう。