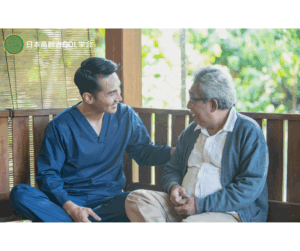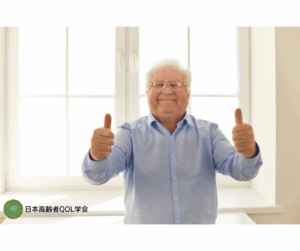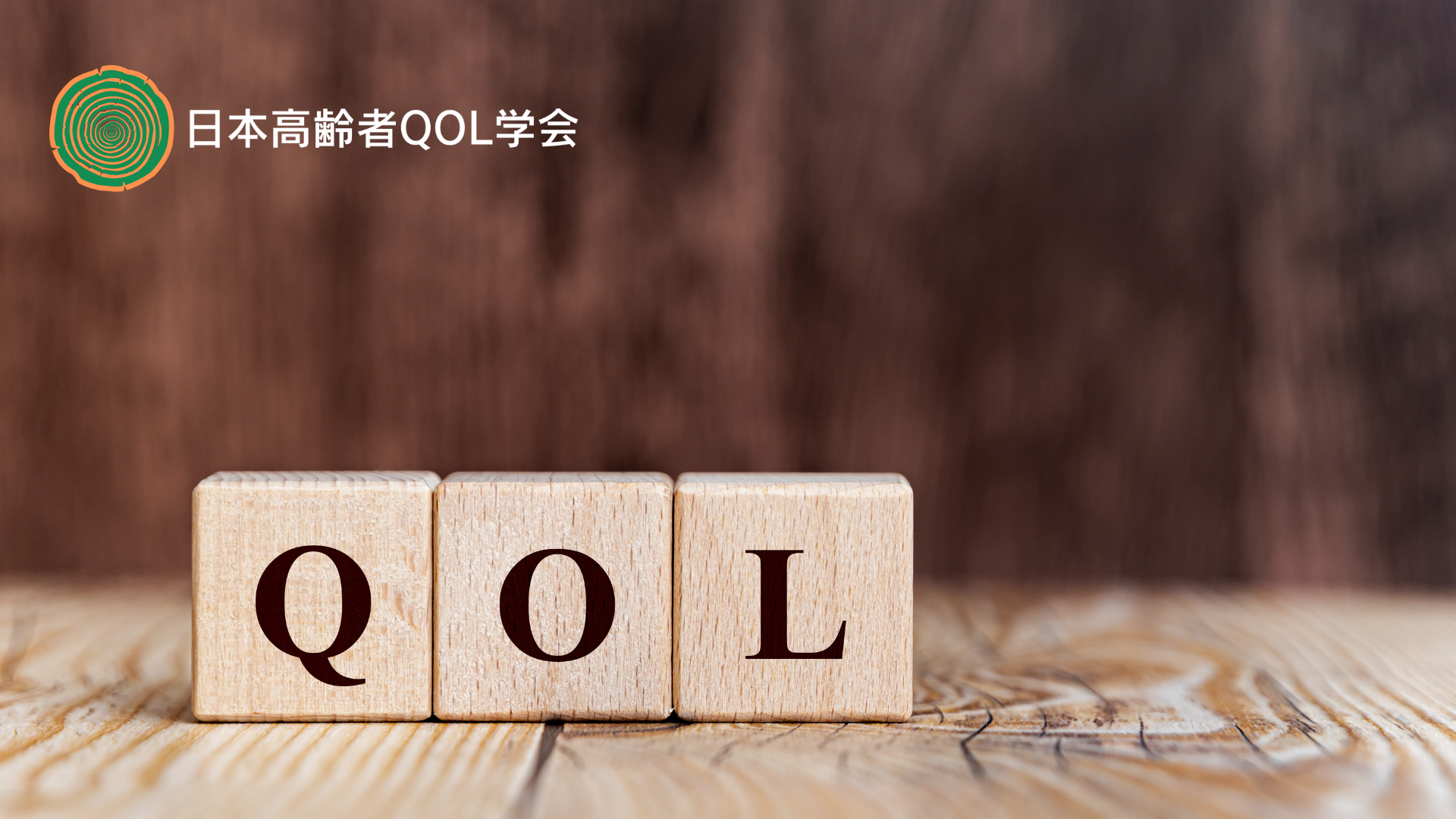
近年、日本では
大規模な地震や豪雨、台風といった
自然災害が多発しています。
災害が起きた際、
高齢者は体力や判断能力の低下から、
迅速な避難が難しくなることがあります。
また、持病を抱えている方も多く、
薬や特別な食料が必要になることも少なくありません。
このブログでは、
高齢者が災害から身を守るために、
事前にできる備えと、
いざという時の具体的な行動について解説します。
大切な親やご家族の命を守るために、
今日からできる備えを始めていきましょう。
1. なぜ高齢者の防災行動が重要なのか?
高齢者は、
災害時に以下のような理由で
危険にさらされやすくなります。
- 身体能力の低下
避難所まで歩くことや、
がれきの中を移動することが困難になります。 - 情報収集の難しさ
聴力や視力の低下により、
防災無線やテレビの情報を十分に得られない場合があります。 - 持病や常備薬
普段飲んでいる薬が手に入らなくなると、
命に関わることもあります。 - 認知機能の低下
状況判断が難しくなり、
適切な避難行動が取れなかったり、
避難を拒否したりすることがあります。
2. 事前にできる3つの備え
災害はいつ起こるかわかりません。
いざという時に慌てないために、
事前にしっかりと準備をしておきましょう。
備え1:安否確認のルールを決める
離れて暮らす親と、
災害時の安否確認方法を事前に決めておきましょう。
- 連絡手段の確認
電話が通じない場合に備え、
SNSや災害用伝言ダイヤル(171)
の使い方を確認しておきましょう。 - 避難場所の共有
親が住む地域の避難場所や
避難経路を把握し、
事前に一緒に確認しておきましょう。
備え2:非常持ち出し袋の準備
非常持ち出し袋は、
災害発生から数日間を過ごすために
必要なものを入れておくものです。
高齢者のために、特別な配慮が必要です。
- 最低3日分、できれば1週間分の常備薬
かかりつけ医と相談し、多めに処方してもらい、
非常持ち出し袋に入れておきましょう。
お薬手帳のコピーも忘れずに! - 水分と栄養補助食品
喉の渇きを感じにくいため、
水分を多く含むゼリー飲料や、
栄養補助食品も準備しておきましょう。 - その他
杖、入れ歯洗浄剤、メガネ、補聴器、
携帯トイレなど、日常生活に不可欠なものを入れておきましょう。
備え3:自宅の安全対策
自宅で被災した場合に備え、
家の中の安全対策も行いましょう。
- 家具の固定
タンスや食器棚が倒れてこないように、
L字金具などで壁に固定しておきましょう。 - 寝室の安全確保
ベッドの近くに、
倒れやすいものを置かないようにしましょう。
3. 高齢者が準備しておきたい、水や食料以外の備蓄品
水や食料以外にも、
高齢者が快適に過ごすために
備えておきたいものがあります。
- 携帯トイレ・消臭袋
断水時に役立ちます。
消臭機能付きの袋や凝固剤と
セットになったものが便利です。 - 衛生用品
ウェットティッシュ、使い捨て手袋、
消毒液、大人用おむつなど。 - 常用薬とお薬手帳
常備薬は最低でも数日分、
できれば1週間分は確保しておきましょう。
お薬手帳のコピーや、
かかりつけ医の連絡先も控えておくと安心です。 - 懐中電灯・携帯ラジオ
停電時に役立ちます。
ラジオは手回し式やソーラー式だと、
電池切れの心配がありません。 - 衣類と防寒具
着替え、下着、防寒具(毛布やフリースなど)
を準備しておきましょう。
特に冬場は、寒さ対策が重要です。 - 杖・入れ歯・メガネ
日常生活に不可欠なものは、
非常持ち出し袋の近くに置いておくか、
予備を準備しておきましょう。
まとめ
高齢者の防災は、
「自分の命は自分で守る」という意識に加え、
周囲のサポートが不可欠です。
このブログで紹介した備えを参考に、
ご家族や地域の皆さんで協力し、
災害時に取るべき行動を確認したり、
必要な備蓄品に関して話をするきっかけになれば幸いです。。