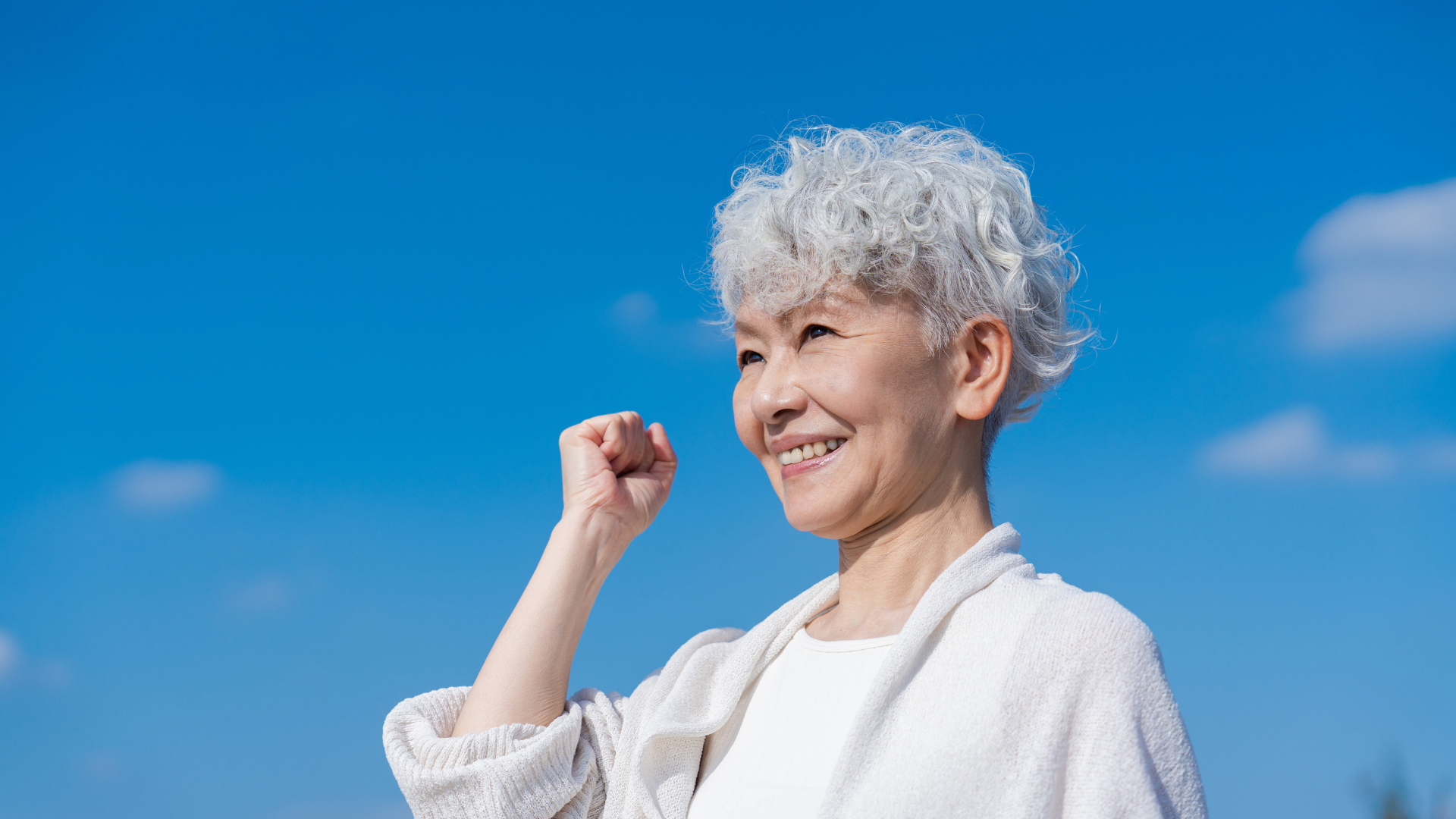「夜になると、なぜかソワソワして歩き回る」
「昼間うとうとしてばかりいる」
認知症の方に見られるこのような睡眠の悩みは、
ご本人だけでなく、
介護するご家族にとっても大きな負担となります。
認知症と睡眠は、
一見関係ないように思えますが、
実は非常に密接な関係にあります。
このブログでは、
認知症の方の睡眠にどのような特徴が見られるのか、
そしてその原因と対処法について解説します。
認知症の方の睡眠を理解し、
より良いケアにつなげるためのヒントを見つけていきましょう。
1. 認知症の方の睡眠にみられる特徴
認知症の進行に伴い、
睡眠には以下のような変化が現れることが一般的です。
- 昼夜逆転
夜に眠れなくなり、
日中にうとうとしてばかりいる
「昼夜逆転」が起こりやすくなります。 - 中途覚醒の増加
一度眠りについても、
夜中に何度も目が覚め、
その後なかなか眠れなくなります。 - 睡眠の質の低下
深い睡眠が減少し、
眠りが浅くなります。 - 夜間せん妄(BPSD)
夜になると、
幻覚や妄想、興奮状態になる
「夜間せん妄」や「夜間徘徊」
が見られることがあります。
2. なぜ認知症と睡眠は密接に関わるのか?
これらの睡眠の問題は、
認知症の病態や、加齢による
体の変化が複雑に絡み合って引き起こされます。
- 体内時計の乱れ
認知症は、脳の機能低下により、
睡眠を司る体内時計の働きが鈍くなります。
これにより、
規則正しい睡眠リズムが保てなくなり、
昼夜逆転を引き起こします。 - メラトニン分泌量の低下
加齢に伴い、
睡眠ホルモン「メラトニン」の
分泌量が減少します。
認知症の場合、
この減少がさらに加速することがあります。 - 不安や混乱
認知症の方は、
見当識障害などにより、
夕方になると周囲が暗くなり、
自分がどこにいるのか分からなくなることで、
不安や混乱を感じやすくなります。
これが、
夜間せん妄や夜間徘徊といった
行動につながることがあります。
3. 認知症の方の安眠のための対処法
認知症の方の睡眠の問題を改善するためには、
ご本人を責めたり、
無理に寝かせようとしないことが大切です。
- 朝に太陽の光を浴びる
体内時計をリセットするために、
朝起きたらまず、カーテンを開けて
太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。 - 日中の適度な活動
日中に体を動かしたり、
散歩に出かけたりすることで、
程よい疲労感が得られ、
夜にぐっすり眠れるようになります。 - 規則正しい生活リズム
毎日同じ時間に食事や入浴をすることで、
生活リズムを整え、
体内時計の乱れを最小限に抑えられます。 - 就寝前の環境づくり
夕方以降は、強い光を避け、
落ち着いた雰囲気を作りましょう。
テレビやスマートフォンの画面は、
メラトニンの分泌を妨げるため、
控えるようにします。 - 不安を取り除く
夜間に不安を感じていたら、
優しく声をかけ、安心させてあげましょう。
まとめ
認知症と睡眠は、
互いに影響し合う関係にあります。
睡眠の問題は、
認知症の症状をさらに悪化させる可能性があるため、
早期の対応が重要です。
このブログで紹介したヒントを参考に、
ご本人に寄り添いながら、
心身ともに安らげる環境を整えていきましょう。