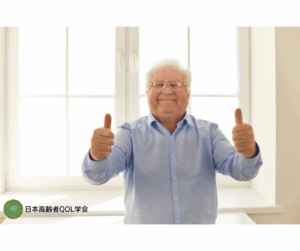日々のケアの中で、
利用者様が同じ話を何度もされることに、
戸惑ったり、忙しさからつい「さっき聞きましたよ」
と言ってしまいそうになったりすることはありませんか?
認知症の進行により短期記憶が乏しくなると、
直前の出来事を覚えていられず、
不安から確認のために同じ話を繰り返したり、
記憶に強く残っている話を繰り返してしまうことがあります。
今回は、
現場で効果があった、
認知症を患う利用者様を
否定せずに安心させるための
具体的な対応法と声かけを5つご紹介します。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:A様
年齢:85歳
性別:女性
既往歴:アルツハイマー型認知症(中症程度)
症状:短期記憶が乏しく同じ話を繰り返す
性格:穏やかで、お話好き
実例1:話の「中身」ではなく「感情」に注目する
利用者様は、
話の内容そのものよりも、
「誰かに話を聞いてほしい」「不安を解消したい」
という感情に動機づけられていることがほとんどです。
・失敗例(心の中で)
「またこの話か…」
とイライラを隠せない。
・成功対応
「そうでしたか!その時は嬉しかったんですね」
と、話の結末や感情に共感を示す。
・効果の理由
内容を訂正せず、傾聴の姿勢を見せることで
「話を聞いてもらえた」という
満足感を得て、不安が解消されやすい。
実例2:繰り返しの「キーワード」で話題を広げる
全く同じ話の繰り返しを避けるため、
話の中に出てきたキーワードを拾って、
別の話題へと自然に誘導します。
・失敗例(心の中で)
「もういい加減にしてほしい」
と遮ってしまう。
・成功対応
A様:「娘とね、両行に行ったのよ」
⇒「旅行ですか!どこに行かれたんですか?」
「今までで一番楽しかった旅行はなんですか?」
「もう一度行くなら、どこに行きたいですか?」
・効果の理由
繰り返しを許容しつつ、
キーワードから会話を深堀することで、
新しい刺激を与え、記憶を探る楽しさに変える。
認知症ケアの方法の1つに
回想法があります。
繰り返しのキーワードから
自然とその方向に持っていくことで、
脳の活性化にも役立ちます。
実例3:「記録」を活用し、毎回同じリアクションを避ける
穏やかな利用者様でも、
毎回全く同じ返答をされると
「この人は私の話を聞いていない」と
感じる場合があります。
小さな違いを見せて、
真摯に聞いている姿勢を伝えましょう。
・失敗例(心の中で)
毎回「へぇ、すごいですね」と
抽象的な返事をする。
・成功対応
「もしかして、その時って○○でしたか?」
A様:「えっ、なんで知ってるの!?」
・効果の理由
このような会話は
利用者様の驚きという感情を動かします。
もし、「前に話したかしら?」
と聞かれたら
「実は…」と
過去の話をちゃんと覚えていることを伝え、
安心感を与えるとともに、
介護職員がちゃんと話を聞いていることを示せます。
実例4:「忙しい」時は時間を区切って伝える
どうしても手が離せない時、
話を遮るのは失礼です。
正直に状況を伝え、
傾聴の時間を約束することで、
利用者様の気持ちを尊重します。
・失敗例
「今は忙しいので後で」
と、冷たくあしらう
・成功対応
「お話をお聞きしたいのですが、
今から5分だけお食事の準備をさせていただけますか?
5分後に必ずこちらに戻ってきて、
続きをお伺いします。」
・効果の理由
今は話を聞けない理由を伝え
「必ず戻る」ことを明確に約束することで
放置されたという不安感を与えずに
一旦待ってもらうことができます。
※約束は必ず守りましょう。
実例5:「別の活動」で意識を切り替える
不安や退屈から同じ話を繰り返している場合、
物理的に意識を切り替える活動を促すことで、
訴えが軽減することがあります。
・失敗例
同じ話を終わらせようとせずに
聞き続けてしまう。
・成功対応
「私もちょうど休憩なので
一緒に窓際でお茶を飲みませんか?」
・効果の理由
場所や動作を変えることで、
脳内の情報をリセットし、
気分転換を促すことができる。
穏やかな方には特に効果的。
まとめ
同じ話の繰り返しは、
認知症の方にとって
「不安の訴え」や「記憶の確認」の行動です。
大切なのは、
内容を訂正することではなく、
その都度「安心感」を提供することです。
A様のような穏やかな方の場合は
その性格を活かし、
上記のような声かけと対応で、
より質の高い、優しいケアを目指しましょう。