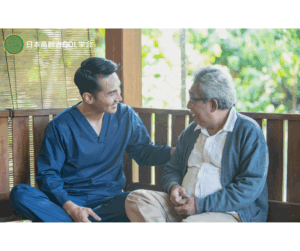日々のケアの中で、
入浴拒否に悩むことはありませんか?
「今日は入らない!」
「家で入っているから大丈夫!」
このように拒否されたり、
時には大声を出されたり…
入浴はとてもデリケートな介助で
今までの生活パターンや
人に見られたくないという羞恥心など
認知機能低下の有無に関わらず
抵抗がある方も多くいます。
今回は、
現場で効果があった、
認知症を患う利用者様を
スムーズに入浴へ誘う具体的な声掛けや
対応法を5つご紹介します。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:T様
年齢:80歳
性別:男性
既往歴:認知症・高血圧・前立腺肥大
状況:生活全般的に意欲が低下している。
自宅で入浴しているからと言い、
デイサービスでの入浴を
毎回大声で怒鳴るように拒否される 。
(実際は家で入浴していない)
意欲低下と強い拒否反応が見られるT様の
プライドを傷つけずに、
スムーズに入浴へと導くための
具体的な対応法を考えていきましょう。
実例1:「入浴」ではなく「健康維持」のための誘導に変える
「お風呂に入りましょう」
というストレートな声かけは、
意欲低下やプライドの強い方には
「指示」と受け取られ、
拒否につながりやすいです。
目的を健康管理にすり替えてみましょう。
・失敗例
「お風呂の時間ですよ」
「お風呂に入りましょう」
と入浴を促す。
・成功対応
「T様、血圧とお体の調子を
専門のスタッフに見てもらう時間です」
と脱衣所に誘導する。
・効果の理由
既往歴などから
皮膚状態の確認や
爪切りなど
健康管理という目的で
脱衣所に誘導することで、
そのまま入浴に繋がる確率が上がります。
実例2:羞恥心に配慮し「自分で決める」選択肢を与える
T様のような男性利用者様は、
特に女性スタッフから裸を見られることへの
強い羞恥心がある場合があります。
この場合は
自分で選べるという感覚を
与えることが重要です。
・失敗例
「ここで脱いでください」
と場所を指定する。
・成功対応
「ここで着替えますか?」
「それとも、
人目の少ない場所にしますか?」
・効果の理由
入浴するかしないかではなく、
どこで着替えるかという選択肢を
提供することで、入浴準備に
意識を向けることができます。
また、
自分で選べるとい安心感にも
繋がります。
実例3:「役割」を与えて、協力を引き出す
意欲が低下しているT様には、
単に指示するのではなく、
頼られていると感じてもらうことが、
行動への動機づけになることがあります。
・失敗例
「服を脱ぐの手伝いますね」
とすべて介助する。
・成功対応
「T様、シャワーの温度を一緒に
確認してもらえますか?」
「ちょうどいい湯加減になったら
教えてください」
・効果の理由
T様をお手伝いする立場に置くことで、
役割を果たすという自尊心の維持に繋がります。
浴室に入ることに慣れてもらうことで
その後の入浴をスムーズに行うことができます。
実例4:「お湯の快適さ」を五感で伝える
認知症の方は、
入浴や更衣室の温度差、浴室の雰囲気など、
五感で感じる不安から拒否することがあります。
言葉だけでなく、
感覚に訴えかける誘導も効果的です。
・失敗例
「気持ちいですよ」
と漠然と伝える
・成功対応
「ここのお部屋暖かいですよ」
「今日は○○の湯なので
いい香りがしますよ」
・効果の理由
湯気の心地よさや香りなど
具体的な感覚に意識を向けることで
浴室へのポジティブなイメージを
与えることができます。
実例5:「自宅での行動パターン」をヒントにする
「家で入浴している」と強く主張するT様に対し、
自宅での入浴習慣を尋ね、
施設内で再現を試みます。
・失敗例
「えっ、家では入っていませんよ」
と否定する。
・成功対応
「いつも何時ごろお入りですか?」
「今日は特別にその時間に近い頃に
ゆっくり入りませんか?」
「いつも使っているお気に入りの
○○(石鹸や入浴剤など)を用意しました」
・効果の理由
自宅のルーティンを尊重し
それを施設で再現しようと努める
姿勢を見せることで、
自分の生活やリズムが守られている
という安心感に繋がります。
まとめ
T様のように
意欲が低下している方への入浴介助では、
『清潔保持』という目的の前に、
『自尊心の保持』を
優先することが大切です。
『指示』ではなく
『お願い』や『協力を求める言葉』に変換し、
T様自身が「自分で決めた」という
感覚を持てるように誘導することが、
大声での拒否を防ぐ最良の方法です。