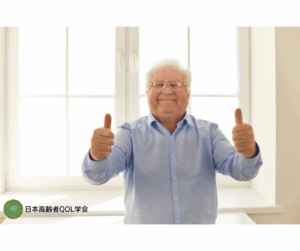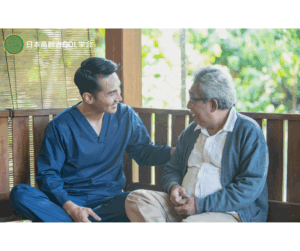みなさんの施設では
移動や歯磨き、入浴の声掛けをすると
大きな声で怒鳴る利用者様や
拒否をする利用者様はいませんか?
あまりに毎回、大声で怒鳴られると
介助者である私たちの心も折れそうに
なりますよね。
しかし、その怒鳴り声は、
利用者様からの助けを求めるサインかもしれません。
今回は、
声掛けや介助に対して大声で怒鳴る
利用者様への対応5選をご紹介します。
お互いに
気持ちよく関われる方法を探していきましょう!
S様の場合、脳血管性認知症の影響で感情のコントロールが難しくなり(怒鳴る症状)、また、無口な性格と、趣味ができていないことによるフラストレーションが蓄積していると考えられます。これらの拒否は、不安と感情の爆発の結果であり、身体的な疾患(閉塞性動脈硬化症など)による不快感や痛みが隠れている可能性も考慮した対応が必要です。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:S様
年齢:87歳
性別:男性
既往歴:脳血管性認知症・脳梗塞
高血圧・閉塞性動脈硬化症
慢性腎不全
性格:基本的に無口。話しかけられるとお話を楽しめる。
麻雀やカラオケ、歴史研究など
趣味はあったが、最近は行えていない。
課題:声掛けや介助に大声で怒鳴りながら拒否をするため、
自宅でも施設でも一人で座って過ごすことが多い。
【拒否の背景にある3つの要因】
S様の場合、
表面的な「怒鳴り」の裏には、
以下の要因が複合的に影響していると考えられます。
- 感情のコントロール障害
脳血管性認知症の影響で、
感情のブレーキが効きにくくなっている。 - フラストレーション
無口な性格に加え、
趣味ができていないことによる
ストレスや喪失感の蓄積。 - 身体的不快・痛み
閉塞性動脈硬化症などの身体的な疾患による、
触れられることへの不快感や痛みが隠れている可能性。
これらの要因が複合的に絡み合っていることを
頭に置きながら、解決策を探っていきましょう!
実例1:介助前の「予告」と「見通し」を徹底する
脳血管性認知症は感情のコントロールが難しく、
急な変化にパニックを起こしやすい特性があります。
介助の直前ではなく、
事前に予告し、
次に何をするかという見通しを伝えることが重要です。
- 予告をする
「S様、10分後に歯磨きをしましょうね」
「その後、カラオケの準備をしませんか」など、
介助の前に次の行動を予告します。 - 理由を説明する
介助の理由を簡潔に伝えます。
『健康維持のため』は効果的です。 - 沈黙は許容する
予告に対してS様が無口であっても、
返事を強要せず、沈黙を許容し、
予告した時間まで待ちましょう。
実例2:怒鳴り始めたら「沈黙」と「場所の変更」で対応する
怒鳴り声は、S様の感情の爆発であり、
言葉による説得は逆効果です。
興奮状態にある時は、
まず刺激の少ない環境へ誘導し、
クールダウンするのを待ちます。
- 怒鳴りを無視
怒鳴りや暴言に対しては
反応せず、沈黙を保ちます。
「静かにしてください」といった注意もせず、
S様から少し距離を取り、
落ち着くのを待ちましょう。 - 場所を変える
「S様、少し広い場所で続きのお話をしませんか」と、
介助を中断し、全く別の場所へ穏やかに誘導します。
場所を変えることで、気持ちの切り替えを促します。 - 身体的介入の回避
興奮中は無理に身体に触れず、
安全な距離を保ちます。
介助の必要性がある場合は、
「落ち着くまで待ちますから、座ってくださいね」
と指示ではなく安心を促す言葉で対応します。
実例3:拒否の背景にある「身体的不快」をアセスメントする
全身の介助を拒否する背景には、
痛みや不快感が隠れている可能性があります。
特に閉塞性動脈硬化症などの既往があるため、
身体状況への配慮が必要です。
- 痛みの確認
拒否の際に、
「どこか痛いところはありませんか?」
「足がしびれていませんか?」と、
痛みの場所や種類を具体的に確認します。 - 介助方法の変更
「入浴が嫌なら、今日は足湯だけにしませんか?」
「歯磨きが嫌なら、うがいだけ先にしませんか?」と、
負担の少ない介助に切り替える代替案を提案します。 - 記録と共有
拒否時のS様の体勢や、
触れると拒否が強くなる箇所を記録し、
職員間で共有します。
必要であれば看護師に報告し、
痛みのケアの有無を相談しましょう。
実例4:「趣味」を切り口に、フラストレーションを解消する
S様が趣味としていた麻雀や歴史研究などに
意識を向けさせ、
できないことへのフラストレーションを
解消する機会を設けます。
- 趣味の再開
「S様、麻雀がお好きでしたね。
今日は○○(介助)の後に、私と麻雀をしませんか」
「歴史研究がお得意でしたよね。
〇〇時代の話を少し聞かせていただけませんか?」と、
S様の得意分野に焦点を当てて声かけます。 - 役割の提供
趣味に関する知識を教えてもらうという形で、
S様に専門家としての役割を与えます。
これにより、
プライドを満たし、
介助で傷ついた自尊心を回復させます。 - 介助の交換条件
「この介助を5分間だけ協力してもらえませんか?
そうしたら、
残りの時間は麻雀の話をじっくり聞かせてもらえますか?」と、
具体的な交換条件を提示し、協力を引き出します。
実例5:介助を「S様のペース」に合わせる工夫をする
介助拒否は、
自分のペースが乱されることへの
抵抗である場合があります。
介助のスピードや順番をS様に委ねることで、
主体性を取り戻してもらえます。
- 介助の主導権を委ねる
「席を移動しますが、どちらに行きたいですか?」と、
介助の主導権をS様に委ねる声かけをしましょう。 - タイマーで時間管理
「入浴は3分で終わらせます。タイマーをセットしますね」と、
終了時間を明確に提示し、
S様が不安を感じないように管理します。 - 無言の介助
介助中に言葉をかけると怒鳴り返す場合は、
目線を合わせ、穏やかに微笑みながら、
無言で介助を試みます。
言葉ではなく、
穏やかな表情や動作で安心感を伝えましょう。
まとめ:穏やかなケアへの近道
S様の介助拒否は、
脳血管性認知症による感情のコントロール障害と
趣味の喪失によるフラストレーションが
複合的に影響した結果です。
怒鳴るという表面的な行動に惑わされず、
まずは沈黙で興奮を鎮めることを優先し、
その後に身体的な不快感がないか、
自尊心を満たせる趣味の話ができないか
を試みることが、穏やかなケアへの近道となります。
コミュニティと講習会のご案内
このように私たちは、
現場ですぐに使えるアイデアを発信しています。
他にも
笑空というコミュニティや
講習会、交流会などを開催しています。
10月は
『腰を守る!
移乗動作と予防体操』
の講習会を開催します。
興味のある方は、こちらから
詳細をご確認ください。
https://ldpdf.hp.peraichi.com/?_gl=1*1qwwv47*_gcl_au*NDM2NjM5MTYwLjE3NTc5MDE2NjEuMTY4NTk1MDIwNi4xNzU5NzE2ODQyLjE3NTk3MTY4NDE.&_ga=2.30308735.139407299.1759716838-1340098679.1757901661