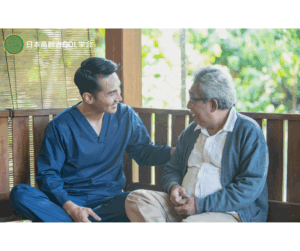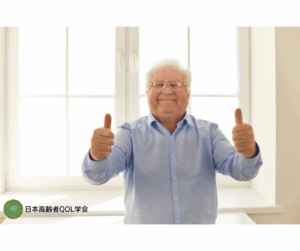みなさんの施設では
ふらつきがあり、転倒リスクが高いのに
自ら動いてトイレなどに行こうとする
利用者様はいませんか?
そんな時は
どのように対応していますか?
特に
せっかちでトイレが近い
利用者様への対応には
気を使うと思います。
今回は、
転倒リスクが高い利用者様の
「自分でやりたい」という気持ちと、
「骨折の危険性」という現実を
両立させるための、
具体的な対応を5つご紹介します。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:K様
年齢:94歳
性別:女性
既往歴:認知症(年相応)、腰部圧迫骨折
大腿骨頸部骨折(オペ済み)
廃用症候群、骨粗鬆症
性格:せっかち、穏やか
課題:足腰が弱っており、ふらつきがある。
トイレが近く、介助を待たずに
自ら移動する。 転倒リスクが高い。
【課題に対する要因分析】
K様のせっかちな性格と、
トイレが近いという要因が合わさることで、
「早くいかなくちゃ」という焦りが生まれ
介助を待つ余裕がなくなってしまいます。
他にも、
以下のようなリスクと要因がります。
- 廃用症候群と筋力低下
骨折の手術や安静により足腰が弱り、
ふらつきが起きやすくなっている。 - せっかちな性格と排泄の切迫感
「間に合わないかもしれない」という
強い焦りが、介助を待つ判断力を奪っている。 - 骨粗鬆症による危険性
転倒=骨折という、
命に関わるレベルの危険性がある。
1. 転倒リスクを軽減し、尊厳を守る実践的対応5選
実例1:「せっかち」な性格に対応する迅速なアクション
K様が自ら立ち上がる前に
介助を開始するためには、
職員がK様の動き出しよりも早く
動く必要があります。
「待たせる時間」を極力なくすことが、
事故を防ぐ鍵です。
- 声かけの簡略化
K様が立ち上がろうとするサイン
(前のめりになる、足を動かすなど)を
見たら長い声かけは不要です。
「はい!行きましょう!」と一言で返し、
すぐに介助を始めましょう。 - 距離の短縮
K様の席の最も近い位置に常に待機するか、
または移動補助具(歩行器など)を
K様が手を伸ばしやすい位置に配置し、
動作の初動をスムーズに
支えられるようにします。 - スピードを意識
介助中の動作は、
乱暴にならない範囲で最大限に早く行います。
K様のせっかちなペースを
否定するのではなく、
それに合わせて介助のスピードを
調整することで、焦りを軽減させます。
実例2:「定時排泄」と「水分調整」による予防的なアプローチ
トイレへの切迫感を減らすことができれば、
自発的な危険な移動を
大幅に減らすことができます。
排泄介助は受動的ではなく、
能動的に行いましょう。
- 定時の声かけ
K様がトイレに行きたいと感じる前に、
定時(例:食後30分、2時間ごとなど)で
排泄への声かけを行います。
「お手洗いはいかがですか?」
「今、行きませんか?」と促し、
排泄パターンを崩さないようにしましょう。 - 水分摂取の計画
水分補給は重要ですが、
一度に多量の水分を摂取すると
トイレが近くなります。
少しずつ、こまめに
水分を摂っていただくよう、
摂取パターンを管理しましょう。 - 誘導語の工夫
排泄への誘導を、
「お手洗いの時間ですよ」ではなく、
「リハビリを兼ねて歩きませんか」など、
泄目的をぼかした声かけにし、
尊厳を守りながら促しましょう。
実例3:「声」や「音」によるプレッシャーセンサーの活用
K様が無言で立ち上がろうとするのを防ぐため、
「何かあればすぐに知らせる」という習慣を
身につけてもらうための環境設定を行います。
- ナースコール利用の訓練
立ち上がる前にナースコールを押す練習を、
リハビリの一環として行います。
「立ちたい時は、
まずこれを押す練習からしましょう」と、
安全を守るための役割を与えて
協力を促します。 - センサーの活用
K様が自分で立ち上がろうとする際、
立ち上がり時に音が鳴るセンサーを設置し、
職員がすぐに察知できる仕組みを作ります。 - 立ち上がり時の声かけ訓練
K様が立ち上がろうとしたら、
職員が反射的に「待って!」と制止する
のではなく、
「大丈夫ですか?」「お手伝いしますよ!」
という肯定的な声かけを統一し、
K様を驚かせないようにします。
実例4:頻回な排泄を「安全な役割」に変換する
あまりに頻回な排泄は、
転倒リスクも伴い、介助者の負担にもなります。
安全な役割や活動を行ってもらうことによって、
「トイレ」という意識を
そらせることができます。
- 軽作業への誘導
塗り絵や制作物に取り組んでいただいたり、
洗濯物を畳むなどの作業へ誘導します。 - 立ち上がりを中断させない
立ち上がりの途中で制止されると、
ストレスに繋がる可能性があります。
中途半端な姿勢で止めず、
「安全に立つ」ことまで一旦介助し、
立位が安定してから声掛けなどを行います。
実例5:移動そのものを「リハビリ」と位置づける
K様の移動を「訓練をしている」という
位置づけに変えてみます。
リハビリ職と連携して、
足腰を鍛える機会として介助を行います。
- リハビリの一環と説明
介助のたびに、
「これは歩行訓練ですね」
「今日は〇メートル歩くのが目標です」と、
移動をリハビリの一環として説明し、
目的意識を持ってもらいます。 - 歩行中の会話
移動中は、
K様のせっかちな意識をそらすため、
K様の好きな話題を話しかけます。
会話で注意を逸らし、
急ぎ足になるのを防ぎます。 - 成功体験の共有
トイレから戻った時に
「今日も転ばずに歩けましたね!」と、
安全に移動できたことを褒め、
「待つこと=安全な移動の成功」という
ポジティブな意識付けを行います。
3. まとめ:迅速な対応と役割の提供
K様への対応は、
「転倒リスクの高さ」と
「せっかちな性格による切迫感」の
ジレンマとの闘いです。
「待って」と制止するのではなく、
「はい、すぐ行きます!」と迅速に対応し、
K様の「自分でやりたい」という意欲を
安全な役割やリハビリに変換することが、
事故を防ぐための鍵となります。
コミュニティと講習会のご案内
このように私たちは、
現場ですぐに使えるアイディアを発信しています。
他にも
笑空というコミュニティや
講習会、交流会などを開催しています。
10月は
『腰を守る!
移乗動作と予防体操』
の講習会を開催します。
興味のある方は、
こちらから詳細をご確認ください。
https://ldpdf.hp.peraichi.com/?_gl=1*1qwwv47*_gcl_au*NDM2NjM5MTYwLjE3NTc5MDE2NjEuMTY4NTk1MDIwNi4xNzU5NzE2ODQyLjE3NTk3MTY4NDE.&_ga=2.30308735.139407299.1759716838-1340098679.1757901661