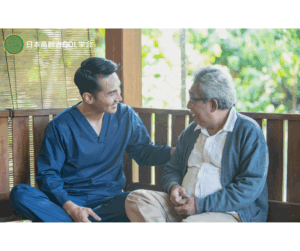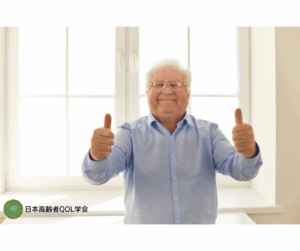「何度声をかけても拒否される」
「理不尽な言葉を浴びせられた」
「自分の気持ちを理解してもらえない」
認知症の利用者様への対応が続き、
心が折れそうになったり、
思わず感情的になってしまいそうになることは
ありませんか?
それは、
あなたが真剣にケアに取り組んでいる証拠です。
介護の現場では、
自分の感情をコントロールすることも、
利用者様をケアするのと同じくらい大切な仕事です。
今回は、
感情的になりそうになった時、
その場ですぐに試せるクールダウンの方法を
5つご紹介します。
目次
1. 感情的にツラくなる要因は?
感情的になる主な要因
- 慢性的なストレスと疲労
睡眠不足や肉体的な疲労が
感情のコントロールを難しくしています。 - 自尊心の低下
繰り返し拒否されたり怒鳴られたりすることで、
自尊心が低下してしまう。 - 共感疲労
利用者様の不安や苦痛に共感しすぎることで、
自分の心が疲弊してしまう。
大切なのは、
「感情的になる自分はダメだ」と責めるのではなく、
「この状況が私を辛くさせている」と
状況に原因があると認識することです。
2. すぐに使えるクールダウン法5選
実例1:物理的に「一歩下がる」と呼吸法
感情を揺さぶられた時は、
まず物理的に利用者様から離れることが、
効果的です。
- 一歩下がる
介助の手を止め、
物理的に一歩後ろに下がりましょう。
この一歩が、
自分と利用者様の間に心の距離を作り、
冷静さを取り戻すきっかけになります。 - 3秒深呼吸
鼻から3秒かけて息を吸い込み、
口から6秒かけてゆっくりと吐き出します。
これを3回繰り返すだけで、
自律神経が整い、すぐに心拍数が落ち着きます。 - 言い訳で中断
介助を中断したい時は、
「すみません、少し水を飲んできますね」
「記録を確認してきます」など、
自然な口実でその場を短時間離れましょう。
実例2:認知の切り替え(原因の特定)
目の前の拒否や暴言は、
「あなた個人への攻撃ではない」と
再認識することが、心を落ち着かせる鍵です。
- 「感情」と「事態」を分ける
相手の行動は認知症や疾患、身体的な痛みによる
『症状』であると割り切りましょう。
「これは利用者様の病気が話している」
と心の中で言葉にすることで、
自分へのダメージを軽減します。 - 30秒ルールの
興奮のピークが去るのを待ちます。
「あと30秒待ってみよう」と区切りをつけ、
その間は無理に話さず沈黙を保ち、
解決を急がないようにします。 - 真のニーズを推測
怒鳴りの裏には「不安」「痛み」「恐怖」が
隠れています。
「なぜ怒っているのだろう?」ではなく、
「今、何に困っているのだろう?」と
考えてみましょう。
実例3:感覚を使ったマインドフルネス
心がパニックに陥りそうになった時、
五感を使って「今、この瞬間」に
意識を集中させ、思考を止める方法です。
- 手の感覚に集中
自分の手のひらをぎゅっと握ったり、
服の素材や自分の足が床に触れている
感触に意識を集中させます。 - 次の行動に集中
ドアノブを握る、ボタンを押すなど、
次に取る具体的な動作に意識を集中させます。 - 色を探す
青いものを3つ探すなど、
感情とは無関係な対象に意識を向けることで、
客観的な視点を取り戻します。
実例4:記録と共有による感情の解放
感情を内に溜め込まず、
安全な形で吐き出すことで、
精神的な負担を軽減します。
- 感情の「命名」
心の中で
「私は今、無力感を感じている」
「これは悲しい気持ちだ」と、
自分の感情に名前をつけましょう。
感情を客観視することで、
コントロールしやすくなります。 - 短い記録(メモ)
休憩中や記録時に、
「〇〇様対応、イライラMAX」
「悲しかった」などと
簡潔に書き出すことで、感情を外に出します。 - 信頼できる同僚への共有
休憩時間などに、
「実はさっき、少しツラくて」と
信頼できる同僚に短時間で吐き出すことで、
共感を得て心のガス抜きをしましょう。
実例5:非言語的コミュニケーションの再構築
自分が感情的になっている時、
利用者様もまた、
あなたの表情や声のトーンから不安を感じ取っています。
- 優しい表情の意識
トイレや鏡で自分の表情を確認し、
意識的に眉間のシワを緩め、
口角を少しだけ上げます。
穏やかな表情は、利用者様だけでなく、
自分自身の心にも安心感を与えます。 - 低い声トーン
感情が昂ると、声のトーンが高くなりがちです。
意識的にゆっくりと低いトーンで話すことで、
利用者様にも落ち着きを、
自分自身にも冷静さを取り戻させます。 - 触れる位置の確認
介助で身体に触れる際は、
相手が驚かないよう、
手の甲など敏感でない場所に
ゆっくりと触れることから始めましょう。
3. まとめ:自分を守ることが、質の高いケアに繋がる
介護職にとって、
自分の感情をコントロールし、
メンタルヘルスを守ることは、
利用者様の安全と質の高いケアに直結します。
ツラい時は一歩下がり、
深呼吸をし、感情に名前をつけ、同僚に頼る。
このシンプルな行動が、
あなたを守る鍵となります。
コミュニティと講習会のご案内
このように私たちは、
現場ですぐに使えるアイディアを発信しています。
他にも、
笑空というコミュニティや講習会、
交流会などを開催しています。
10月は
『腰を守る!移乗動作と予防体操』
の講習会を開催します。
興味のある方は、
こちらから詳細をご確認ください。