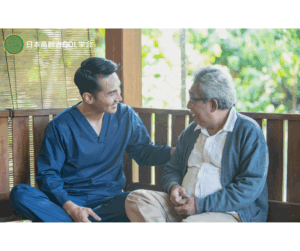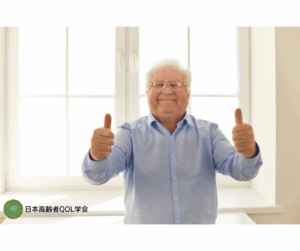介護施設で働く中で、
「家に帰りたい」「迎えに来て」と
訴える利用者様への対応に悩むことはありませんか?
帰宅願望は、認知症の方が感じる
「今いる場所がどこかわからない」
「安心できる場所にいたい」という
不安のサインであることがほとんどです。
この訴えをただ否定せず、
いかにして安心感と納得感を提供できるかが、
ケアの質を左右します。
今回は、
利用者様の気持ちに寄り添いながら、
穏やかに安心感を与えるための
具体的な対応と声かけを5つご紹介します。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:M様
年齢:78歳
性別:女性
既往歴:アルツハイマー型認知症・糖尿病・高血圧
症状:昼食後に帰宅願望あり。
「家に帰る!」と大きな声をだすこともある。
性格:ややヒステリック。
家族関係:夫と2人暮らし。夫が介護しようとすると、
強い口調で拒否をすることで喧嘩になる。
夫は介護疲れ気味。近くに息子がいるも
口は出すが、介護には消極的。
実例1:昼食直後の『環境調整』
大声を出す興奮状態を未然に防ぐため、
昼食直後の対応が鍵となります。
集団のざわつきや手持ち無沙汰などを回避して、
落ち着いて過ごせる環境へ素早く誘導します。
・失敗例
「まだ帰りませんよ」と
理由を説明する。
・成功対応
歯みがきやトイレ誘導などの喧騒から離れ
静かでゆっくりと過ごせる場所を作り
「食後のお茶です」と休憩を促す。
手持ち無沙汰になると帰宅願望が現れる場合、
食器の下膳やお盆を拭いてもらうなどの
お手伝いを依頼する。
・効果の理由
静かな食事の時間から、
急にザワザワし始めると
不安を感じることがあるため、
静かな環境に移動することで興奮を抑える。
手持ち無沙汰になると
何をしたらいいのか不安になるため
お手伝いなどの役割を作る。
実例2:ヒステリックな訴えに対する対応
M様が大声を出して興奮し始めたら、
まずは他の利用者様から離し、
刺激の少ない静かな場所へ誘導します。
興奮している時に言葉で反論・説明をしても
火に油を注ぐだけです。
・失敗例
「静かにしてください」
「みなさんが見ていますよ」
と注意する。
・成功対応
(落ち着いたトーンで)
「M様。どうしましたか?」
「私が話を聞くので静かなところに行きましょう」
(しばらく沈黙して話を聞く)
・効果の理由
M様が興奮を吐き出し切るのを
静かに待ち、
落ち着いたトーンで接することで、
興奮による悪循環を断ち切る。
実例3:「夫への不満」をひたすら聴く
M様の帰宅願望の裏には、
夫への不満や、
自宅でのストレスのフラッシュバック
があると考えられます。
「家へ帰りたい」を
「夫への不満」や「自宅でのストレス」と捉え、
気持ちを吐き出してもらう時間を設けます。
・失敗例
「ご主人が心配されていますよ」
と夫を擁護する。
・成功対応
「本当に大変な思いをされてきたんですね。」
と共感を示す。
・効果の理由
家族にも理解してもらえなかった感情を
第三者に聞いてもらうことで、
心が楽になり、安心感に繋がり、
帰宅への執着を和らげる。
実例4:次の予定に意識を向けさせる
M様は、
自分の意向が無視されることに
ヒステリックになる可能性があります。
「帰りたい」という訴えを完全に否定せず、
次の予定に意識を向けさせることで、
気持ちを切り替えます。
・失敗例
「帰る時間には早すぎます」
と理由を伝える。
・成功対応
「お帰りになる準備ですね、承知いたしました。」
「では、その前に、少しだけこのお茶を飲んでいただき、
〇〇の作業を片付けてしまいましょう。
それが終わったら、
お迎えが来るまでゆっくり待ちましょうね。」
・効果の理由
「帰る」という目的を否定せず、
「〇〇の作業」という
短期的な目標を挟むことで、
M様に行動の順序を納得してもらう。
実例5:「自宅での役割」を施設で再現し、安心感を強化する
M様が自宅で得意としていたことや、
安心できた活動があれば、
それを施設内の静かな場所で再現します。
これは、
興奮状態を沈静化させるのに有効です。
・失敗例
「ここは施設だからできません」
と諦めさせる。
・成功対応
「M様がお家でいつもなさっていた
(編み物など)を、
ここで少しだけやってみませんか?」
「○○を私に教えてください」
・効果の理由
家でやっていた安心できる活動
を今・ここで実行することで、
今いる場所を
安心できる場所だと認識する。
まとめ
M様への対応では、
「興奮させないこと」と
「気持ちの居場所を作ること」が
最優先です。
特に興奮状態では論理的な説明は逆効果です。
まず共感と沈静化を徹底し、
M様の内面にある「不安」や「不満」を
第三者である介護スタッフが受け止めることで、
自分は大切にされているという安心感を提供しましょう。