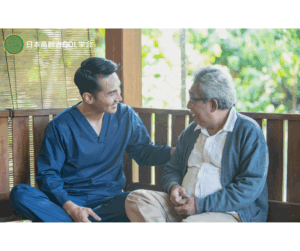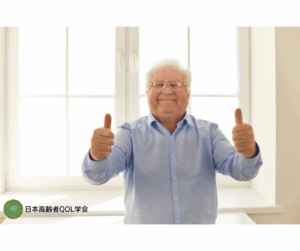みなさんの施設では、
帰り際や送迎の際に
「今日のタクシー代です」
「コレあげる」
などと金品を渡そうとする利用者様は
いませんか?
お気持ちは嬉しいですが、
施設の規則でできない場合も
多いかと思います。
今回は、
なにかと金品を渡そうとする利用者様の
気持ちを尊重しながら、上手に対応する方法5選を
ご紹介していきます。
利用者様の基本情報
まずは、
今回の対応を検討するにあたっての
利用者様の基本情報を共有しておきましょう。
利用者様名:M様
年齢:85歳
性別:女性
既往歴:アルツハイマー型認知症・躁うつ病
糖尿病・白内障
性格:基本的に穏やかでお話好き。
意にそぐわないと感情的になる。
世話を焼くことが好き。
課題:帰り際や送迎の際に、
「今日のお礼」「家でたくさん採れたから」
と金品を渡そうとしてくる。
実例1:感謝の気持ちは受け取り、「別の形」で代替案を提示する
金品を受け取れない理由をストレートに伝えることは、
M様の「お礼をしたい」という気持ちを否定し、
感情的になる可能性があるため避けましょう。
M様の気持ちを尊重し、
まずは感謝の気持ちを伝え
代替案をお伝えすることで
『お礼をしたい気持ち』を無下にせずに
対応することができます。
- 感謝を伝える
「M様のそのお気持ちだけで、十分すぎるほど嬉しいです」
と、金品には触れずに丁重に辞退し、
まずは感謝の気持ちを受け取ります。 - 代替案の提示
「M様のお気持ちは大切に心にしまいますので、
代わりに、お手紙やメッセージカードとして
気持ちを伝えてもらえませんか?」と、
金品ではない形でお礼をする方法を提案します。 - 代替案の提示
「そのお金は、M様がご家族と会う時に、
一緒に美味しいお菓子を買うために
大切にとっておいてくださいね」と、
M様自身の楽しみのために使うことを勧めます。
実例2:ルールを伝える際、個人的な理由ではなく「公平性」を強調する
「私は受け取れません」と
職員個人の問題にするのではなく、
施設全体のルールであることを明確に伝え、
M様の自尊心を尊重しながら協力を求めます。
- ルールの明文化
「大変ありがたいのですが、
実は、皆さんを平等にサポートするため、
私たち職員は個人的な贈り物を受け取れないという
共通のルールになっています」と、
理由を簡潔に伝える。 - 見本になってもらう
「M様はいつも皆のお手本になってくださいます。
このルールを守っていただけると、
私たち職員も安心して他の方のお手伝いができます」と、
M様を立てて協力を求める。 - 理由を伝える
「もし私が受け取ってしまうと、
他の職員がM様を特別扱いしていると思われて、
M様が施設で過ごしにくくなってしまうかもしれません」
と、M様を守るためであることを伝えます。
実例3:「役割」の提供で「役に立ちたい」というニーズを満たす
M様の
「世話を焼きたい」「役に立ちたい」という意欲を、
金品を渡す行為ではなく、
施設内で役立つ役割として発揮してもらうことで、
気持ちを昇華させます。
- 共同作業へ誘う
「M様にお礼をいただくのは恐縮ですが、
M様には私たちがお礼を言いたいことがあります。
帰りの準備を
一緒に手伝っていただけませんか?」と、
別の作業への協力を依頼する。 - 貢献感の提供
金品を渡そうとしていた手を、
「では、その手で
このタオルを畳むのを手伝っていただけますか?
この仕事はM様にしかできません」と、
別の活動に切り替えさせる。 - 感謝の記録
活動後には、
「M様のおかげでスムーズに終われました!
今日のM様のお手伝いのことは、しっかり記録に残して、
皆にM様が頑張ってくださったことを伝えますね」と、
口頭や記録でM様の功績を褒め、貢献感を満たします。
実例4:金品の現物を「一時的に預かる」形で対応する
金品が視界にあると、
渡そうとする行動が繰り返されるため、
紛失・盗難トラブルを防ぐためにも、
一時的にスタッフが管理します。
- 預かりの依頼
金品を手に持っている場合は、
「大変重要なものですので、
また次回来られた時にすぐお渡しできるよう、
私が大切にお預かりしますね」と伝え、
辞退しつつ、管理の安全性を強調します。 - 場所の明確化
「今からナースステーションの鍵のかかる金庫に入れておきますね。
ご安心ください」と、
安全な保管場所を具体的に伝えることで、
M様の不安を取り除きます。 - 家族への報告
預かった金品があることを、
必ず介護記録に詳細に記載するとともに、
その日のうちにご家族へ報告し、
預かりを継続するか、ご自宅へ持ち帰っていただくか
指示を仰ぎます。
実例5:ご家族へ「感謝の気持ちの代弁」を依頼する
M様が「渡したい」という気持ちを
溜め込んで感情的になるのを防ぐため、
ご家族に協力してもらい、
間接的に感謝を受け止める機会を作りましょう。
- 気持ちの説明
ご家族に、
「M様が、日頃の感謝を金品で表そうとされています。
これはM様の優しさや貢献意欲の表れなので、
その気持ち自体を否定しないでほしい」と
M様の心理を説明します。 - 伝言の依頼
ご家族からM様へ、
「施設の方から
『M様の優しいお気持ちは十分届いています』と聞いたよ」
などと伝えてもらい、
間接的に感謝を受け止めてもらうよう依頼します。 - 代わりの贈り物
ご家族に、金品ではなく
M様が手作りした品(折り紙、編み物など)を
職員へ渡す役割を担っていただくことで、
M様の献身的な意欲を発揮できる場を設けてもらうよう
提案します。
緊急時の対応と記録の徹底
M様が感情的になり、
金品を無理に押し付けようとしたり
、投げつけたりする場合は、冷静に
「お気持ちは嬉しいですが、ルールなので受け取れません」
と伝え、その場から距離を取り、
他のスタッフに状況を伝えてすぐに応援を呼びます。
- 記録の徹底
いつ、何を、どのように渡そうとしてきたか、
そしてどのように対応し、
現在どこに預かっているかを必ず記録し、
職員間で共有しましょう。
まとめ
M様のように
「何かお礼をしたい」
と思われる方に対しては
その気持ちをまずはしっかりと
受け止めることが大切です。
M様のパターン以外にも
お金の支払いが不安で渡そうとする
利用者様もいるかと思います。
その場合は、
「毎月利用料金と一緒に
口座から引き落としになっています」
などのように
ちゃんと受け取っているという旨を伝え
安心感に繋がる声掛けをしましょう。