親の介護が必要になったら、まず最初にやること

「もしかして、親に介護が必要になる日が来るかもしれない…」
仕事や子育てで忙しい日々が続いていると
親との連絡の機会が減ってしまうことってありますよね。
ある日突然、
親の体調が悪化したり、
認知症の症状が顕著になったりして、
「どうしよう?」と
途方に暮れる日が来るかもしれません。
今回のブログでは、
いざ親の介護が必要になった時に、
慌てずに最初の一歩を踏みだせる方法を解説します
仕事との「両立」を視野に入れながら、
何から始めるべきか、
具体的なステップと心構えについて、
分かりやすく解説していきます。
1. 「親の介護」の予兆を捉える:異変に気づいたら
親の介護が必要になるサインは、
必ずしも急な病気や事故ではありません。
多くの場合、日々の小さな変化の中に隠されています。
- 認知機能の変化に気づく
- 以前は自分でできていた買い物の計算間違いが増える、
- 同じ話を何度も繰り返す、薬の飲み忘れが頻繁になる。
- 電話で話していても、話のつじつまが合わなくなることが増えた、など。
- 身体機能の変化に気づく
- 以前より歩く速度が著しく遅くなった、
- 手すりがないと階段の上り下りが辛そう、
- よく転ぶようになった、など。
- 生活習慣の変化に気づく
- 部屋が散らかり始めた、
- 身だしなみに気を遣わなくなった、
- 食事がきちんと摂れていないようだ、
といった様子が見られたら要注意です。
もし、
このような「あれ?」と感じる異変に気づいたら、
それが「親の介護」のスタートラインに立つ最初の合図です。
この段階で、
漠然とした違和感を捉えることが、
後のスムーズな対応につながります。
2. 最初の一歩:地域包括支援センターに連絡する
親の介護が必要だと感じた時、
まず最初にすべきことは、
地域包括支援センターに連絡することです。
ここが、
あなたが頼れる「総合窓口」となります。
- 地域包括支援センターとは?
- 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、
介護、医療、福祉など様々な面からサポートする中核機関です。
市区町村が設置しており、
専門職(保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなど)が配置されています。
- 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、
- なぜ最初に連絡すべきなのか?
- 無料の総合相談窓口
どんな些細な悩みでも無料で相談できます。
介護の知識がなくても、
専門家が状況を丁寧に聞いてくれます。 - 情報提供と連携
親の状況に合わせて、
適切な医療機関の紹介、介護保険制度の利用方法、
地域の介護サービスの情報提供など、必要な情報を教えてくれます。
また、
病院や行政、他の専門機関との連携もサポートしてくれます。 - 客観的な視点
家族だけでは感情的になりがちな介護の問題に、
客観的な視点でアドバイスをくれます。
- 無料の総合相談窓口
3. 次のステップ:親の状態を「見える化」し、「介護保険」を申請する
地域包括支援センターに相談したら、
次は親の状態を客観的に評価し、
介護サービスを受けるための手続きに進みます。
- 医師の受診
- 地域包括支援センターの助言を受け、
親が専門医(かかりつけ医、脳神経内科、精神科、物忘れ外来など)
を受診できるように促します。
この際、
親が受診を拒否することもありますが、
「健康チェックのついでに」
「最近よく眠れていないみたいだから先生に相談してみよう」など、
親が受け入れやすい言葉を選ぶのがポイントです。
医師の診断(意見書)は、介護保険の申請に必要です。
- 地域包括支援センターの助言を受け、
- 介護保険の申請:「要介護認定」への道
- 親の住む市区町村の窓口、
または地域包括支援センターで介護保険の申請を行います。 - 申請後、親の自宅に調査員が訪問し、
心身の状態や生活状況を調査します(訪問調査)。 - 主治医の意見書と訪問調査の結果をもとに、
介護認定審査会が審査を行い、
「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」
のいずれかの認定が出されます。 - ポイント
認定には数週間~1ヶ月以上かかる場合があるため、
早めに申請することが重要です。
この認定結果によって、
受けられるサービスの種類や量が決まります。
もしも
認定の結果に不満がある場合は
再度、認定調査を依頼できることもあります。
その際は、
担当のケアマネジャーなどに
相談してみましょう。
- 親の住む市区町村の窓口、
4. ケアプラン作成とサービス利用の開始
要介護認定が出たら、
いよいよ具体的な介護サービスの利用へと進みます。
- ケアマネジャーとの面談
- 要支援の認定を受けた場合は
地域包括支援センターの担当者が、
要介護の認定を受けた場合は
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、
親と面談を行います。 - ケアマネジャーは、
親の心身の状態、生活環境、希望などを詳しく聞き取り、
それに基づいて「ケアプラン」を作成します。
ケアプランは、
どのようなサービスを、
どのくらいの頻度で利用するかを具体的に示した計画書です。 - ポイント
この面談には、できる限りあなたも同席し、
親の意向やあなたの希望(仕事との両立に関する制約など)
をしっかり伝えることが重要です。
- 要支援の認定を受けた場合は
- サービス内容の決定と利用開始
- ケアプランに沿って、
訪問介護(ホームヘルパー)、
通所介護(デイサービス)、
短期入所生活介護(ショートステイ)、
福祉用具のレンタルなど、
必要なサービスが決定され、利用が開始されます。
- ケアプランに沿って、
5. 仕事との「両立」を見据えた準備と心構え
親の介護が始まると、
あなたの生活や仕事にも大きな影響が出ます。
スムーズな「両立」のためには、事
前の準備と心構えが重要です。
- 職場の理解を得る
- 介護休業や介護休暇など、
会社にどのような制度があるかを確認しましょう。
上司や人事担当者に状況を伝え、
理解と協力を得られるように相談してみてください。 - ポイント
事前に情報を共有することで、
急な介護の必要が生じた際もスムーズに連携でき、
不要なストレスを避けられます。
- 介護休業や介護休暇など、
- 頼れる「チーム」を作る
- 一人で抱え込まないことが何よりも大切です。
兄弟姉妹、親戚、地域の友人、
そして介護サービス事業者、ケアマネジャーなど、
親を支える「チーム」を作りましょう。
役割分担を明確にし、
定期的に情報交換を行う場を持つと良いでしょう。
- 一人で抱え込まないことが何よりも大切です。
- 自身の心身のケアも大切に
- ビジネスケアラー(働きながら介護する人)は、
ストレスや疲労が蓄積しやすい立場です。
自身の健康を犠牲にしては、
親を支え続けることはできません。 - ポイント
短時間でも良いので趣味の時間を持つ、
信頼できる人に話を聞いてもらう、
定期的に体を動かすなど、
リフレッシュできる時間を作りましょう。
- ビジネスケアラー(働きながら介護する人)は、
まとめ:不安を乗り越え、親と自分のQOLを守るために
親の介護が必要になった時、
多くの現役世代は不安と戸惑いを感じるでしょう。
しかし、
事前に知識を持ち、
適切なステップを踏むことで、
余裕を持って進めることができます。
まず最初にすべきは、
迷わず地域包括支援センターに連絡することです。
※基本は地域包括支援センターですが、
民生委員や社会福祉協議会などに馴染みがあれば
まずは、そちらに相談しても大丈夫です
そこから
親の状態の把握、
介護保険の申請、
ケアプランの作成といったプロセスは、
親の介護と仕事の「両立」を実現するための最初の1歩です。
一人で抱え込まず、
専門機関や家族、職場の仲間など、
周囲の協力を得ながら、あなた自身も健康で、
親と共に心穏やかな日々を送るために、
今回の内容が助けになれば幸いです。


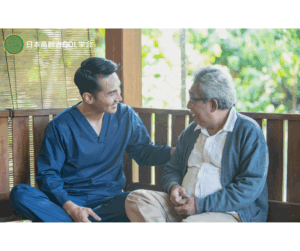

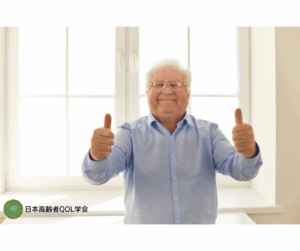



COMMENT