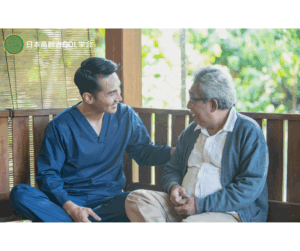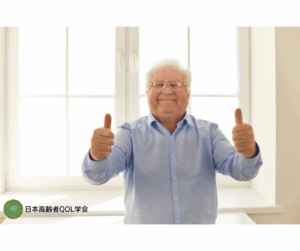「家に帰りたい」。認知症の介護をしているご家族にとって、
この言葉は辛く、
対応に悩むことが多いのではないでしょうか。
特に、
親が今いる場所が「家」であるにもかかわらず、
何度も「帰りたい」と訴える帰宅願望は、
介護者の心をかき乱し、大きなストレスとなります。
なぜ、
認知症の親は帰宅願望を抱くのでしょうか?
それは、
単に「家に帰る」ことを意味しているのではなく、
もっと深い不安や混乱が隠されているからです。
このブログでは、
帰宅願望が起こる理由を理解し、
親の気持ちに寄り添いながら、
穏やかに接するための具体的な対応策を解説します。
1. 認知症における「帰宅願望」とは?
帰宅願望は、
認知症の周辺症状(BPSD)の一つです。
これは、
記憶障害によって、
今いる場所を「自分の家」と認識できなくなってしまう
ことが主な原因です。
- 時間や場所の混乱
認知症が進行すると、
今がいつで、どこにいるのかという
見当識が失われます。
そのため、
自分の家であっても
「ここは知らない場所だ」と感じてしまい、
「本当の家」に帰りたいと訴えるのです。 - 過去の記憶に戻る
過去の記憶にさかのぼり、
自分が若かった頃の家や、
子どもを育てていた頃の家を
「本当の家」だと認識している場合があります。 - 心の不安の現れ
「家に帰りたい」という言葉の裏には、
「ここは自分の居場所ではない」
「自分はここにいてはいけない」といった
強い不安や孤独感が隠されています。
これは、
認知症によって自分の役割や存在意義が
揺らいでいる状態の現れでもあります。
帰宅願望は、
親があなたを困らせようとしているわけではなく、
病気によって引き起こされる、
心からのSOSであることを理解することが、
対応の第一歩です。
2. 帰宅願望が起きた時のNG行動と適切な対処法
親から「帰りたい」と訴えられた時、
どのように対応すればいいのでしょうか。
ついやってしまいがちなNG行動と、
親の気持ちに寄り添う適切な対処法を知っておきましょう。
NG行動:否定する、正論で説得する
- 「ここがあなたの家だよ」と否定する
親は、今いる場所が家ではないと心から信じています。
そのため、
あなたが事実を伝えても混乱するだけで、
信頼関係を損なう原因になります。 - 「もう夜だから帰れないよ」と正論で説得する
論理的な説明は認知症の方には通じません。
かえって親は、
「なぜ帰れないのか」とパニックになり、
不安や怒りを増大させてしまいます。
適切な対処法:共感し、安心させる
- まずは共感する
「家に帰りたいのですね、寂しいね」と、
親の気持ちに寄り添い、不安を受け止めましょう。
「家」という言葉を否定せず、
親の感情に共感することで、
安心感を与えることができます。 - 目的を探る
「家に帰りたい」という言葉の裏には、
「夕食の準備をしなきゃ」
「子どもを迎えに行かなきゃ」といった
目的が隠されている場合があります。
「どうして家に帰りたいのですか?」
と優しく問いかけ、
その目的を一緒に探してみましょう。 - 注意をそらす
「夕飯の準備、一緒に手伝ってくれませんか?」や
「お茶でも飲みませんか?」と誘いかけ、
別のことに注意を向けさせましょう。
好きな音楽をかけたり、
昔の写真を見せたりするのも有効です。 - 「一緒に探す」という態度を見せる
「わかりました。では、一緒に帰りましょうか」と、
一時的に親の言葉を受け入れ、
一緒に家の中や外を少し歩いてみましょう。
しばらく歩くと疲れて、
「やっぱり家で休もうか」となることがあります。 - 安心できる環境を整える
日頃から、親が安心して過ごせる環境を整えましょう。
好きなものを部屋に置く、
なじみのある音楽をかける、
など、親にとっての
「居場所」を再認識してもらうことが大切です。
3. 介護施設での帰宅願望:専門家との連携
親が介護施設に入所している場合も、同様に帰宅願望が現れることがあります。
- 施設のスタッフと連携する: 帰宅願望の頻度や、それが起こる時間帯などを施設のスタッフと共有し、対応策を一緒に考えましょう。
- 面会のタイミングを工夫する: 施設に面会に行く際、親が不安になってしまう場合は、面会時間を短くしたり、親が落ち着いている時間帯に訪問するなど、工夫してみましょう。
まとめ
認知症の帰宅願望は、
親の深い不安や混乱から生まれる、
心からのSOSです。
「否定しない」「共感する」「安心させる」
という3つの原則を大切に、
親の言葉の裏にある本当の気持ちを探ることで、
親との間に信頼関係を築き、
穏やかな介護生活を送ることができるでしょう。