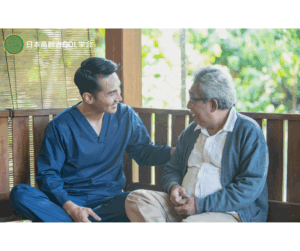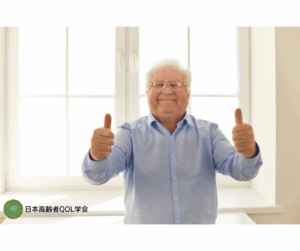「認知機能」と聞くと、
「記憶力」を一番に思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、
私たちが日常生活を送る上で欠かせない認知機能は、
一つの能力だけではなく、
複数の要素が複雑に絡み合って成り立っています。
これらの要素を理解することは、
認知症の早期発見や予防だけでなく、
自分の脳の得意なこと、
苦手なことを知る上でも非常に役立ちます。
このブログでは、
認知機能を構成する6つの主要な要素について解説します。
これらの要素をバランス良く鍛えることで、
いつまでも健やかな脳を保ち、
自分らしい生活を送りましょう。
1. 記憶力(Memory)
記憶力は、
最もよく知られている認知機能の要素です。
出来事や情報を覚えて、
必要な時に思い出す能力を指します。
- 短期記憶
数秒から数分間、
情報を一時的に保持する能力
(例:電話番号をメモするまでの間、覚えておく) - 長期記憶
数時間から数年、
あるいは一生にわたって情報を保持する能力
(例:子どもの頃の思い出、自転車の乗り方)
認知症の初期に最も低下しやすいのが、
新しい出来事を覚える短期記憶です。
2. 注意力(Attention)
注意力は、
特定の物事に意識を集中させ、
それ以外の刺激を無視する能力です。
- 持続的注意
一つの作業に集中し続ける能力
(例:読書や映画鑑賞) - 選択的注意
2つ以上の情報の中から、
必要な情報だけを選び取る能力
(例:騒がしい場所で、相手の話を聞き取る) - 分配的注意
複数のことを同時に行う能力
(例:料理をしながら会話をする)
注意力が低下すると、
ケアレスミスが増えたり、
会話が途切れがちになったりすることがあります。
3. 実行機能(Executive Function)
実行機能は、
目標を立て、計画を立て、それを実行し、評価する
一連の能力です。
- 計画力
物事を順序立てて考える能力
(例:旅行の計画を立てる) - 柔軟な思考力
状況の変化に合わせて、
考え方や行動を変える能力
(例:急な予定変更に対応する) - 問題解決能力
課題を見つけ、
解決策を考える能力
実行機能が低下すると、
段取りが悪くなったり、
衝動的な行動が増えたりすることがあります。
4. 言語機能(Language)
言語機能は、
言葉を理解したり、話したり、書いたり、
読んだりする能力です。
- 言語理解
相手の言葉や文章の内容を理解する能力。 - 言語表出
自分の考えを言葉で表現する能力。
言語機能が低下すると、
「あれ」「これ」といった代名詞が増えたり、
言葉が出てこなくなったりすることがあります。
5. 空間認識能力(Visuospatial Function)
空間認識能力は、
物体や空間の形、大きさ、位置関係を把握する能力です。
- 場所の認識
今いる場所がどこなのかを認識する能力。 - 物体の認識
物の形や立体感を把握する能力。 - 道案内
地図を読んだり、道順を覚えたりする能力。
空間認識能力が低下すると、
慣れた道で迷子になったり、
物の置き場所が分からなくなったりすることがあります。
6. 社会的認知(Social Cognition)
社会的認知は、
他者の感情や意図、社会的な状況を理解し、
適切に行動する能力です。
- 感情認識
相手の表情や声のトーンから感情を読み取る能力。 - 共感
相手の立場になって物事を考える能力。 - 社会性の維持
社会的なルールやマナーを守って行動する能力。
社会的認知が低下すると、
相手の気持ちを汲み取ることが難しくなり、
人間関係のトラブルにつながることがあります。
まとめ:多角的なアプローチで脳を鍛える
認知機能の低下は、
これらの要素が一つずつ、
あるいは複数同時に衰えることで起こります。
認知症の予防には、
記憶力だけでなく、
注意力や実行機能、言語機能など、
多角的に脳を鍛えることが重要です。
読書、パズル、新しい場所への旅行、
友人との会話、運動など、
日々の生活に様々な刺激を取り入れることで、
すべての認知機能をバランス良く維持していきましょう。