親の介護が頭をよぎったら?ビジネスケアラーのための準備と心構え

「最近、親の様子が少しおかしい…」
「もしかして、介護が必要になる日が来るのだろうか?」
仕事と家庭に追われる日々の中で、
ふと親のことが頭をよぎり、
漠然とした不安を感じる人は少なくありません。
特に、
親が離れて暮らしている場合、
変化に気づきにくいこともありますよね。
しかし、
その「違和感」を見逃さないことが、
親と自分自身のQOL(生活の質)を
守るための第一歩となります。
今回のブログでは、
親の介護が現実味を帯びてきたときに、
仕事と介護の両立(以下ビジネスケアラー)をどう準備し、
どう対応すればよいのか。
認知症などの症状を察知するポイントから、
もしもの時の対応、
そして日頃からの親との関わり方まで、
具体例を交えながら、
あなたの不安を少しでも和らげるヒントをお届けします。
1. 「あれ?」と思ったら… 認知機能低下や身体機能低下を察知するポイント
多くのビジネスケアラーが直面するのが、
「変化」に気づく難しさです。
特に認知症の初期症状は、
加齢によるものと区別がつきにくく、
見過ごされがちです。
認知機能低下のサイン
・同じ話を繰り返す、新しいことを覚えられない
「この前も話したでしょ?」と言っても、
「え?聞いてないよ」と繰り返す。
つい先日あった出来事を覚えていない。
さっき話したばかりの隣人の噂話をもう一度話し始めるなど。
・日付や曜日、場所が分からなくなる
今日が何月何日か、何曜日か分からないことが増える。
「今日はどこへ行くんだっけ?」と、
普段行っている場所の名前を忘れる。
・物忘れが激しくなる(ヒントがあっても思い出せない)
鍵や財布の置き場所を頻繁に忘れるだけでなく、
探す手伝いをしても「どこに置いたんだっけ?」
と思い出せない。
・段取りが悪くなる、料理の味が変わる
以前は完璧だった料理の味が急に濃くなったり薄くなったりする。
簡単な料理でも手順が分からなくなり、時間がかかる。
・意欲の低下、無気力になる
趣味だった外出をしたがらなくなる
テレビを見ていてもぼんやりしている時間が増える
など、明らかに活動性が落ちる。
・性格が変わったように感じる、怒りっぽくなる
些細なことで感情的になったり、
今まで温厚だった親が急に頑固になったりする。
被害妄想のような発言が増えることも。
身体機能低下のサイン
- 歩き方が不安定になる、転びやすくなる
以前より歩く速度が遅くなり、フラフラする。
家の中でよくつまずく、転んだという話を聞くようになる。 - 着替えや身だしなみが疎かになる
同じ服を何日も着ていたり、
以前はきれい好きだったのに身だしなみが乱れる。
入浴を嫌がるようになるなど。 - 食欲の変化、体重の減少
食事が進まない
買い置きの食品がそのままになっている
逆に同じものばかりを食べるようになる
それに伴い体重が減る など - 排泄の失敗が増える
トイレに行く回数が増えたり、
間に合わなかったりする。
夜間のおねしょなど - 薬の管理ができていない
薬を飲み忘れている、
あるいは重複して飲んでいる形跡がある。
薬のシートが溜まっているなど。
これらのサインは、
親からの「助けて」という無言のメッセージかもしれません。
日頃から注意深く親の様子を観察し、
変化があれば記録しておくことをおススメします。
2. もし、認知症などの症状が疑われたらどうするか?
「もしや?」と感じたら、
迷わず行動を起こすことが大切です。
早期発見・早期対応が、親のQOL維持、
そして介護の負担軽減に繋がります。
ステップ1:情報を整理し、具体的な状況を把握する
- 気づいたことを記録する
どんな状況で、いつ、どのような言動があったのか、
具体的にメモしておきましょう。
後で医師や専門家に伝える際に役立ちます。 - 情報を共有できる家族がいれば相談する
兄弟姉妹や配偶者など、
親をよく知る人と情報を共有し、
客観的な意見を聞いてみましょう。
自分だけでは気づかないサインがあるかもしれません。 - 親の生活状況を確認する
冷蔵庫の中身、光熱費の支払い状況、
郵便物の確認など、日常生活に支障が出ていないか、
できる範囲で確認しましょう。
ステップ2:専門機関に相談する
いきなり病院に連れて行くのが難しい場合でも、
相談できる窓口はたくさんあります。
- 地域包括支援センター
高齢者の総合相談窓口です。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが常駐しており、
無料で相談に乗ってくれます。
認知症に関する専門的なアドバイスや、
医療機関への紹介、地域の介護サービスの情報提供など、
幅広いサポートが受けられます。
まずはここに電話してみるのが最もおススメです。 - かかりつけ医:
親が普段から通っている医師がいれば、
その医師に相談してみましょう。
親の健康状態をよく理解しており、
適切な専門医(脳神経内科、精神科、物忘れ外来など)
を紹介してくれる可能性があります。 - 市区町村の高齢福祉課など
各自治体の窓口でも、
認知症に関する相談や支援制度の案内を行っています。
ステップ3:医療機関の受診を促す
専門機関に相談し、
受診が必要と判断されたら、
親に受診を促します。
この際、
親が抵抗を示すことも少なくありません。
- 伝え方の工夫
「物忘れがひどいから病院に行こう」
と直接的に言うと、
親は傷ついたり、拒否したりする可能性があります。
「最近、体調はどう?」
「持病の薬をもらいに行くついでに、
最近気になっていることを先生に相談してみない?」
など、親が受け入れやすい言葉を選びましょう。
「最近、物忘れがひどいから病院に行こう」
と言ったら
「ボケてなんかいない!」と激怒。
そこから、
受診拒否となり治療が遅れたり
そのまま介護拒否につながるケースが
意外と多いです - 付き添い
可能であれば、一緒に病院へ付き添い、
医師に親の普段の様子や気づいたことを伝えましょう。
親が医師に上手に伝えられないこともあります。
3. 日頃からの親との関わり方:介護に備える「心の貯金」
親の介護は、
ある日突然始まるものではありません。
日頃からの関わり方によって、
親の変化に気づきやすくなり、
いざという時の連携もスムーズになります。
コミュニケーションを密にする
- 定期的な連絡
電話やメッセージアプリ(LINEなど)で、
定期的に連絡を取りましょう。
声を聞く、文章を見るだけでも、
親の様子や感情の変化に気づきやすくなります。 - 会話の質を高める
忙しいからといって、
義務的な連絡にならないよう注意しましょう。
親の話に耳を傾け、共感する姿勢が大切です。
用があるときだけ連絡をして
そのついでに体調を聞いている
という方が多い印象です
毎日でなくてもいいので
週1回など定期的に連絡を取ることで
日常の些細な変化を伝えやすくなります
また、
介護が必要になったときも
フランクに会話ができることはとても重要です - 共通の話題を持つ
親の趣味や好きなテレビ番組、
地元のニュースなど、共通の話題を見つけることで、
会話が弾みやすくなります。
情報を共有し、理解を深める
- 介護に関する情報収集
普段から介護保険制度や地域の介護サービスについて
少しずつ情報を集めておきましょう。
いざという時に慌てずに済みます。 - 自身の状況を伝える
仕事が忙しいこと、家族のことなど、
自身の状況を親に理解してもらうことも大切です。
過度な心配をかけず、
しかし協力体制は築けるよう、
バランスの取れたコミュニケーションを心がけましょう。 - エンディングノートや財産状況の確認
話しにくいことかもしれませんが、
親の体力が元気なうちに、
エンディングノートの有無や、
財産状況、延命治療の意思などについて、
少しずつ話し合っておくことも重要です。
物理的な環境を整える
- 自宅のバリアフリー化
手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更など、
転倒リスクを減らすための簡単な改修を検討しましょう。 - 見守りツールの検討
離れて暮らす場合、見守りカメラや人感センサー、
スマート家電など、
デジタル技術を活用した見守りツールの導入も有効です。
親のプライバシーを尊重しつつ、安心感を高めることができます。
自身の心身のケアも忘れずに
ビジネスケアラーは、
仕事と介護のダブルケアで最も負担が大きい立場の一つです。
親を支えるためにも、
自分自身の健康を最優先に考えましょう。
- 休息を取る
短時間でも良いので、リフレッシュする時間を作りましょう。 - 相談相手を持つ
友人、家族、職場の同僚など、
信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも、
気持ちが楽になります。 - 無理はしない
全てを一人で抱え込まず、
必要であれば地域のサービスや専門家の助けを
借りることをためらわないでください。
まとめ:不安を「準備」と「つながり」に変える
親の介護が頭をよぎる瞬間は、
誰にとっても不安なものです。
しかし、
その不安を放置せず、
「もしかしたら」というサインにいち早く気づき、
適切な知識と準備をすることで、
親のQOLを保ち、自分自身の負担も軽減することができます。
日頃からの密なコミュニケーションと、
親の変化を注意深く見守る目
そして、
もしもの時には一人で抱え込まず、
地域包括支援センターなどの専門機関を積極的に活用すること。
働く皆さんが、
介護の不安を少しでも軽減し、
親と共に心穏やかな日々を送れるよう、
この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。


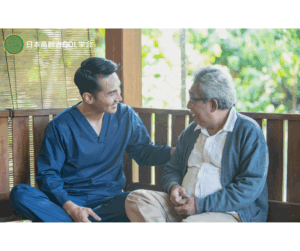

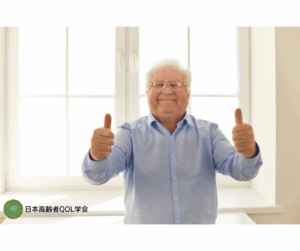



COMMENT