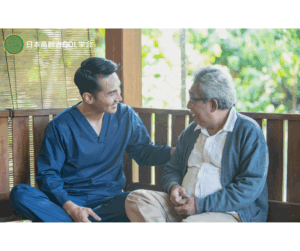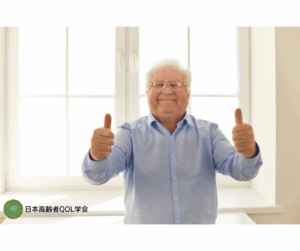「誰かが私のお財布を盗んだ!」
「大切な指輪がない、あなたが見つけたんでしょう?」
認知症の介護をしていると、
物とられ妄想に直面することがあります。
これは、
大切な物をなくした際に、
「誰かが盗んだ」と思い込んでしまう症状です。
介護者であるあなたは、
「そんなことないよ」と否定したくなりますが、
それはかえって相手の怒りや不安を増大させてしまう原因になります。
このブログでは、
物とられ妄想がなぜ起こるのかを理解し、
相手の気持ちに寄り添いながら、
穏やかに接するための具体的な対処法を解説します。
適切な対応を知ることで、
相手との信頼関係を壊すことなく、
穏やかな介護生活を送るためのヒントを見つけていきましょう!
1. 認知症における物とられ妄想とは?
物とられ妄想は、
認知症の中核症状ではなく、
周辺症状(BPSD)の一つです。
これは、
記憶障害が原因で起こる、
非常に苦しい症状です。
- 記憶障害が原因
親は物を置いた場所を忘れてしまいます。
しかし、
「物をなくした」という現実だけが残り、
「誰かが盗んだに違いない」と解釈してしまいます。
これは、相手にとって
「盗まれた」という妄想が
一つのつじつまの合う現実だからです。 - 不安と混乱
自分の記憶が曖昧になり、
相手は非常に強い不安や混乱を感じています。
その不安が
「物が盗まれた」という疑いとなって現れるのです。 - 自尊心の低下
自分で物を管理できなくなったという現実から、
相手は自尊心を傷つけられています。
そのため、
「私が忘れたのではない、誰かが盗んだのだ」
という理由で、自分のプライドを守ろうとします。
物とられ妄想は、
相手が意地悪で言っているわけではなく、
認知症という病気が引き起こす、
症状であることをまず理解することが大切です。
2. 物とられ妄想が起きた時のNG行動と適切な対処法
物とられ妄想に直面した時、
私たちはどうすればいいのでしょうか。
ついやってしまいがちなNG行動と、
相手の気持ちに寄り添う適切な対処法を知っておきましょう。
NG行動:否定する、責める
- 「そんなことないよ」「盗るわけないでしょ」と否定する
相手は「盗まれた」と心から信じています。
そのため、
あなたが否定することで、
「私を信じてくれない」と感じ、
信頼関係を損なう原因になります。 - 「またその話?」「いい加減にして」と責める
相手は自分の記憶障害に不安を抱えています。
責められることで、
その不安がさらに増大し、パニックになったり、
攻撃的になったりすることがあります。 - すぐに「はい、これ」と物を見せる
親の気分によっては、
「あなたが隠していたんでしょ!」
と怒りを増幅させてしまうことがあります。
適切な対処法:共感し、一緒に探す
- まずは共感する
「大変だったね」「それは心配だね」と、
相手の気持ちに寄り添い、
不安を受け止めましょう。
相手は「自分の気持ちをわかってくれた」と感じ、
落ち着きを取り戻しやすくなります。 - 一緒に探す
「一緒に探してみようか?」と、
優しく声をかけましょう。
この時、
「どうせ探しても見つからないだろう」
という態度を見せず、真剣に探す姿勢が大切です。 - 違うことに注意を向ける
しばらく探しても見つからない場合は、
「お茶を飲みながら、もう一度どこに置いたか思い出してみようか」
などと、別のことに注意を向けさせましょう。 - 見つかった時の対応
探している物が偶然見つかった場合は、
「こんなところにあったよ!よかったね」と、
明るく伝えましょう。
この時、
「なんでこんなところに置いたの?」
と責めないことが大切です。 - 物の置き場所を工夫する
よく使う物は、
決まった場所に戻せるように工夫しましょう。
また、隠したり、
ポケットに入れたりする癖がある場合は、
貴重品を見つけやすい場所に複数用意しておくことも有効です。
3. 事前にできる予防策:安心できる環境作り
物とられ妄想を完全に防ぐことは難しいですが、
事前にできる予防策もあります。
- 物の定位置を決める
誰が見てもわかるように、
物の定位置を決め、
一緒に確認する習慣をつけましょう。 - 貴重品は預かる
大切な書類や通帳、高価な装飾品などは、
相手の許可を得て、
あなたが管理するようにしましょう。 - 安心できる言葉かけ
日頃から「いつでも頼ってね」「何かあったら言ってね」と、
相手に安心感を与える言葉をかけることで、
不安感を軽減させることができます。
まとめ
物とられ妄想は、
認知症の症状の一つであり、
あなたを困らせようとしてやっているわけではありません。
大切なのは、
「病気で苦しんでいる」という事実を理解し、
「否定しない」「責めない」「共感する」
という3つの原則を忘れないことです。
相手の心に寄り添い、
安心できる環境を整えることで、
物とられ妄想と穏やかに向き合うことができるでしょう。