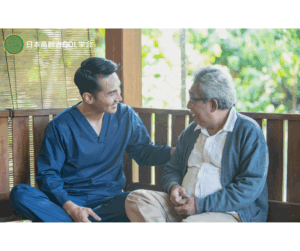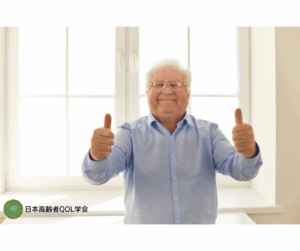レビー小体型認知症(DLB)は、
認知症の中でも4~5%の方が発症していると
言われている認知症の1つです。
しかし、
その症状はアルツハイマー型とは大きく異なり、
正しい知識がないと対応に戸惑ってしまうことが少なくありません。
特に、
幻視やパーキンソン病に似た症状が現れるため、
ご本人もご家族も強い不安を感じることがあります。
このブログでは、
レビー小体型認知症の主な特徴と、
日々のケアで知っておきたいポイントを解説します。
この病気への理解を深めることで、
ご本人もご家族も安心して向き合えるヒントを見つけていきましょう。
1. レビー小体型認知症の主な特徴
レビー小体型認知症は、
脳内に「レビー小体」という
特殊なたんぱく質が蓄積することで発症します。
このレビー小体が、
記憶や運動を司る神経細胞を徐々に破壊していくのです。
特徴1:認知機能の変動
レビー小体型認知症の最も大きな特徴は、
認知機能が日によって、
あるいは時間帯によって大きく変動することです。
- 症状の例
ある時は会話がスムーズにできるのに、
数時間後にはぼんやりして反応が鈍くなる、
といったように、
「できること」と「できないこと」の差が激しいことがあります。
特徴2:リアルな幻視
幻視は、
レビー小体型認知症の初期から現れやすい症状です。
- 症状の例
実際にはいない人や虫、動物がはっきりと見える、
といったリアルで具体的な幻視が見られます。
ご本人にとっては現実と区別がつかないため、
恐怖や混乱を引き起こすことがあります。
特徴3:パーキンソン病に似た運動症状
手足の震えや筋肉のこわばりといった、
パーキンソン病に似た症状が現れます。
- 症状の例
- 歩行障害
すり足で小刻みに歩く、転びやすい、
といった症状が見られます。 - 動作緩慢
体の動きが遅くなり、
無表情になることがあります。
- 歩行障害
特徴4:レム睡眠行動障害
夢の中で体が動いてしまう
「レム睡眠行動障害」も、
レビー小体型認知症の初期から現れることが多い特徴です。
- 症状の例
寝ている間に大声を出したり、
手足をばたつかせたりして、
まるで夢を見ているように体を動かしてしまいます。
2. レビー小体型認知症のケアで知っておきたいポイント
これらの特有の症状に対し、
ご家族はどう対応すればいいのでしょうか。
幻視への対応
- 否定しない、でも肯定もしない
「そんなものはいないよ」と否定すると、
ご本人は「私の言うことを信じてくれない」と感じ、
不安や不信感を強めます。
かといって、「そうですね」と肯定すると、
幻視がより強く定着してしまう可能性があります。 - ご本人の感情に寄り添う
「それは怖いね」「大変だね」と、
ご本人の感情に寄り添い、安心感を与えましょう。 - 別のことに注意を向ける
「一緒に温かいお茶でも飲みませんか?」などと、
別の行動を促して、話題をそらしてみましょう。
認知機能の変動への対応
- ご本人の状態に合わせてケアする
ぼんやりしている時は無理に話しかけず、
落ち着いて見守りましょう。
はっきりしている時には、
コミュニケーションやレクリエーションを楽しみましょう。 - 焦らない
体調が良い時に一気にやろうとせず、
無理のないペースでケアを進めることが大切です。
運動症状への対応
- 転倒予防
歩行が不安定なため、
自宅の段差をなくす、手すりをつけるなど、
転倒を予防するための環境を整えましょう。 - リハビリの活用
専門家によるリハビリを受けることで、
運動機能の維持・改善が期待できます。
レム睡眠行動障害への対応
- 寝具の工夫
柔らかい布団やベッドを使う、
ベッドの周りに物を置かないなど、
ご本人やご家族が怪我をしないよう工夫しましょう。
まとめ
レビー小体型認知症は、
多様な症状が現れるため、
介護が非常に難しい病気です。
しかし、
ご本人の言動が「病気」によるものであると理解し、
その時々の症状に合わせて柔軟に対応することで、
穏やかな介護生活を送ることができます。
一人で抱え込まず、
専門医やケアマネジャーに相談し、
適切なサポートを受けることが何よりも大切です。
このブログが、
レビー小体型認知症と向き合うご家族の一助となれば幸いです。